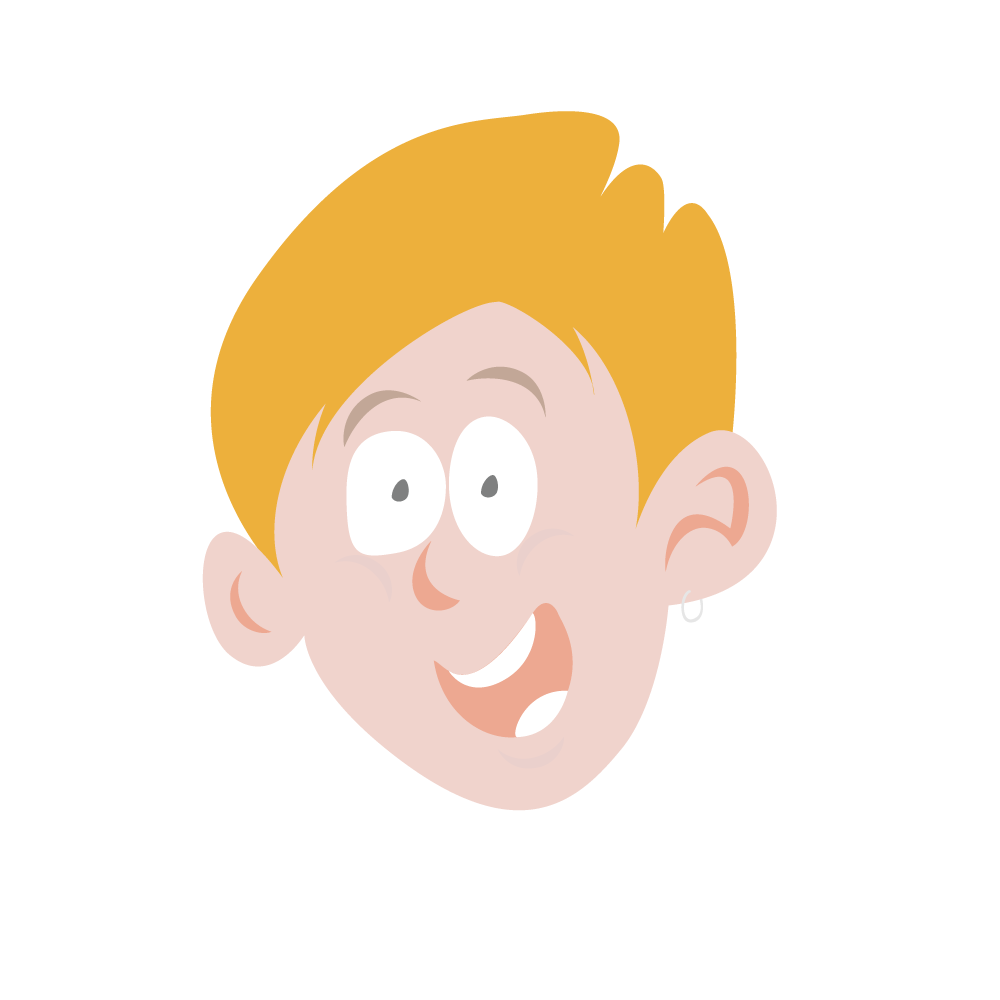ねばねば研究所・イメージ
「納豆をおやつ代わりにできないか」と考えていませんか。
ダイエット中の間食は悩ましいですが、納豆は栄養面で多くのメリットがあります。
低糖質で血糖値の上昇が緩やかな点はもちろん、満腹感が得られ腹持ちがいいのも魅力です。
さらに、食物繊維による便秘解消、乳酸菌の脂質代謝サポート、内臓脂肪の肥満予防への期待など、健康や美容を支える要素が豊富です。
納豆菌が腸の状態を整え免疫力アップに貢献したり、抗酸化作用のある成分、ビタミンやアミノ酸が含まれている点も見逃せません。
この記事では、粒とひきわりの違いやプリン体への注意点にも触れながら、おすすめのレシピまで詳しく解説します。
ポイント
- 納豆がダイエット中の間食に適している理由
- 納豆に含まれる健康・美容成分の具体的な働き
- 「粒」と「ひきわり」の効果的な選び分け
- おやつとして食べる際の注意点と簡単アレンジ
納豆をおやつ代わりに選ぶメリット
ダイエット中の間食に最適

ねばねば研究所・イメージ
ダイエット中に空腹を感じた際、おやつ(間食)に何を選ぶかは非常に重要です。
納豆は、ダイエット中の間食として最適な選択肢の一つと言えます。
その最大の理由は、「低カロリー」「低糖質」「高たんぱく質」という、ダイエットをサポートする三拍子が揃っている点にあります。
市販されている納豆1パック(約50g)あたりのカロリーは、製品にもよりますが約80〜90kcal程度です。
これは、例えば糖質や脂質が多いチョコレート(板チョコ半分で約150kcal)やポテトチップス(小袋で約300kcal)と比較しても、圧倒的に低カロリーです。
さらに見逃せないのが、たんぱく質の含有量です。
納豆1パックには約8.3gのたんぱく質が含まれているとされます。
これは、ゆで卵1個強(約7〜8g)に匹敵する量です。ダイエット中は食事制限によって、エネルギー源として筋肉が分解されやすくなるため、筋肉量を維持し基礎代謝を低下させないことが成功の鍵となります。
基礎代謝が落ちると、消費カロリーが減り「痩せにくく太りやすい体」になってしまうため、間食で手軽にたんぱく質を補給できる納豆は、非常に合理的です。
他のヘルシーとされる間食と比較しても、納豆の優秀さが分かります。
| 食品(1食あたりの目安) | カロリー(目安) | たんぱく質(目安) | 糖質(目安) |
|---|---|---|---|
| 納豆(1パック 50g) | 約92kcal | 約8.3g | 約2.5g |
| プレーンヨーグルト(100g) | 約56kcal | 約3.6g | 約4.9g |
| 木綿豆腐(1/4丁 75g) | 約55kcal | 約5.3g | 約0.9g |
| アーモンド(10粒 約10g) | 約61kcal | 約2.1g | 約1.0g |
| バナナ(中1本 約100g) | 約93kcal | 約1.1g | 約21.4g |
※数値は「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」等を基にした目安です。
このように比較すると、納豆はカロリーあたりのたんぱく質量が非常に効率的でありながら、糖質を低く抑えられることがわかります。
特に豆腐は納豆と同じ大豆製品で非常に低糖質ですが、満腹感や手軽さの面では、パックを開けてすぐ食べられる納豆に分がある場合もあるでしょう。
ダイエット中の間食は「悪」ではなく、「何を食べるか」が重要です。
栄養価の低いお菓子で空腹を紛らわすのではなく、納豆のように体を構成する栄養素を補給できる食品を選ぶことが、健康的なダイエット成功への近道です。
低糖質で血糖値の上昇が緩やか

ねばねば研究所・イメージ
納豆がダイエット中の間食に適している大きな理由の一つに、糖質の含有量が極めて低いことが挙げられます。
前述の通り、納豆1パック(50g)あたりの糖質量は、製品にもよりますが約2.5g程度です。
これは、他の炭水化物が多いおやつ、例えばおにぎり1個(糖質約40g)や、甘い菓子パン(糖質50g以上)とは比べ物にならない少なさです。
糖質を多く含む食品を食べると、血液中のブドウ糖濃度、いわゆる「血糖値」が急激に上昇します。
血糖値が急上昇すると、すい臓から「インスリン」というホルモンが大量に分泌されます。
インスリンは血糖値を下げるためにブドウ糖を細胞に取り込ませる働きをしますが、同時に余ったブドウ糖を脂肪(中性脂肪)に変えて、体内に蓄積するよう促す働きも持っています。
つまり、血糖値の急上昇(血糖値スパイク)を繰り返すことは、肥満に直結しやすいのです。
GI値( グリセリック・インデックス )とは
食品を食べた後の血糖値の上昇度合いを示す指標を「GI値」と呼びます。
GI値が高い食品ほど血糖値が急上昇しやすく、低い食品ほど上昇が穏やかです。
大豆製品は総じてGI値が低い「低GI食品」に分類され、納豆もその代表格です。
納豆は低糖質かつ低GI食品であるため、食後の血糖値上昇が非常に緩やかです。
実際に、2型糖尿病の治療を行っている医師が、自身の血糖値コントロールのために様々な間食を試したという報告があります。
その医師が、手術後の空腹時に納豆(タレなし、薬味あり)を1パック食べた後の血糖値変動を測定したところ、上昇はわずか5〜10mg/dL程度であったとされています。
これは、血糖値への影響がほとんどないに等しい数値です。
このように、血糖値の変動を最小限に抑えられる納豆は、インスリンの過剰分泌を防ぎ、脂肪の蓄積リスクを低減できる理想的なおやつです。
糖質制限中の方や、血糖値が気になり始めた方にとっても、安心して取り入れられる食品と言えます。
満腹感が続き腹持ちがいい

ねばねば研究所・イメージ
ダイエットが失敗する一般的な原因の一つに、「空腹感に耐えられない」ことが挙げられます。
カロリーを抑えたとしても、すぐにまたお腹が空いてしまっては、次の食事で食べ過ぎたり、別のおやつに手を出してしまったりする原因になります。
その点、納豆は「満腹感」と「腹持ちの良さ」において非常に優れています。
この腹持ちの良さの秘密は、納豆が豊富に含む「たんぱく質」と「食物繊維」にあります。
1. たんぱく質による満腹感
前述の通り、納豆は高たんぱく質食品です。
たんぱく質は、糖質や脂質に比べて消化吸収に時間がかかります。
胃腸に長く留まるため、物理的に満腹感が持続しやすいのです。
また、たんぱく質の摂取は、満腹感をもたらすホルモンの分泌を促すとも言われています。
2. 食物繊維による満足感
納豆には食物繊維も豊富です。
食物繊維、特に水溶性食物繊維は、胃の中で水分を吸って膨らみ、容積を増やす性質があります。
これにより、少量でも胃が満たされ、満足感を得やすくなります。
ある医師の報告によれば、手術の合間の小休止に納豆1パックをゆっくりと食べたところ、強い空腹感が改善され、次の手術まで集中力が持続したとされています。
しっかりとした食べ応えと、持続する満足感は、多忙な現代人の間食にもぴったりです。
食べ方の工夫で、さらに満足度アップ!
納豆の食べ方を工夫することで、満腹感を高めることができます。
- よく混ぜて食べる:納豆をよくかき混ぜると、ネバネバ(ポリグルタミン酸)が空気を含んでフワフワになります。これにより食感が良くなるだけでなく、カサが増して満足感が得やすくなります。
- ゆっくり食べる:満腹中枢が働き始めるまでには、食べ始めてから約20分かかると言われています。納豆1パックをじっくり味わって食べることで、食べ過ぎを防げます。
- 「ケーキ納豆」風に食べる:パックのまま混ぜずに、まるでケーキをスプーンですくうように食べる方法も紹介されています。混ぜないことでネバネバ感が抑えられ、「ご飯が欲しくなる」という欲求を抑えやすいというメリットがあるようです。
- 「時間差食べ」:まず1パック食べ、10分ほど待ってみます。それでもまだ空腹を感じるようであれば、もう1パック食べる、という方法です。この「待ち時間」を設けることで、脳が満腹感を感知する時間を稼ぎ、結果として食べる量を抑えることができます。
このように、納豆はそれ自体の栄養特性に加え、食べ方を工夫することで、ダイエット中の強い味方となる満腹感を提供してくれます。
食物繊維で便秘解消、乳酸菌が脂質代謝を補助

ねばねば研究所・イメージ
納豆は、腸内環境を整える「腸活」の観点からも、おやつとして非常に優れた効果が期待できます。
特に「食物繊維」と「乳酸菌(発酵食品であること)」の二つの側面が重要です。
食物繊維による便秘解消サポート
納豆には、食物繊維が豊富に含まれています。納豆1パック(50g)には、約3.0g〜4.8gの食物繊維が含まれているとされます。
これは、野菜ジュース1杯やリンゴ半分以上に相当する量です。
食物繊維には「不溶性食物繊維」と「水溶性食物繊維」の2種類があり、納豆には両方がバランス良く含まれています。
- 不溶性食物繊維:便のカサを増やし、腸を刺激してぜん動運動を活発にします。
- 水溶性食物繊維:便を柔らかくして排出しやすくするほか、腸内の善玉菌のエサとなります。
ダイエット中は食事量が減ることで、便のカサが不足し便秘になりがちです。
便秘になると、腸内に老廃物が溜まるだけでなく、腸内環境が悪化し、むくみや血行不良、さらには代謝の低下を引き起こす可能性があります。
おやつに納豆を取り入れることで、このダイエットの天敵である便秘の解消をサポートできるのです。
乳酸菌と脂質代謝
納豆は発酵食品であり、納豆菌だけでなく、製造過程で「乳酸菌」も含まれることがあります。
乳酸菌は腸内細菌のバランスを整え、善玉菌を増やす働きがあります。
近年、腸内環境が肥満や脂質代謝と深く関連していることが分かってきています。
腸内環境が整うことで、脂質代謝が改善し、体脂肪が蓄積されにくい体質になる可能性が期待されています。
さらに効果を高める食べ方として、同じく発酵食品である「キムチ」と組み合わせる「キムチ納豆」もおすすめです。
キムチに含まれる植物性乳酸菌と、納豆の納豆菌・食物繊維が相乗効果を生み、より強力な腸活効果が期待できます。
納豆をおやつにすることは、単に空腹を満たすだけでなく、腸内環境を根本から整え、便通改善や脂質代謝のサポートといった、痩せやすい体質づくりにも貢献するのです。
納豆菌が腸を整え免疫力を高める
納豆を納豆たらしめている最大の特徴、それは「納豆菌」の存在です。
納豆菌は、正式には「枯草菌(こそうきん)」の一種であり、非常に生命力が強いことで知られています。
多くの乳酸菌が胃酸によって死滅してしまうのに対し、納豆菌は「芽胞(がほう)」という硬い殻のようなバリアを形成する能力を持っています。
これにより、胃酸や胆汁にも負けず、生きたまま腸に到達することができるとされています。
このタフさが、納豆菌が腸活において非常に優秀である理由です。
生きて腸に届いた納豆菌は、以下のような働きをすると考えられています。
- 腸内環境の改善:腸内で善玉菌(ビフィズス菌など)のエサとなり、その増殖を助けます。
- 悪玉菌の抑制:納豆菌が作り出す物質が、腸内の悪玉菌の働きを抑えることが報告されています。
- 整腸作用:腸内の腐敗を防ぎ、腸の働きを正常に保つサポートをします。
そして、腸内環境が整うことは、単に便通が良くなる以上の意味を持ちます。
実は、人間の免疫細胞の約7割は腸に集中していると言われており、腸は「人体最大の免疫器官」とも呼ばれています。
納豆菌によって腸内環境が整い、善玉菌が優位な状態が保たれることは、腸管の免疫システムを正常に機能させ、体全体の免疫力を高めることに直結します。
ダイエット中は栄養バランスが偏ったり、ストレスがかかったりして体調を崩しやすい側面もありますが、おやつに納豆を取り入れることは、健康維持と免疫力サポートの観点からも非常に有益です。
おやつで手軽に「腸活」と「免疫ケア」ができるのは、納豆ならではの大きな強みですね。
内臓脂肪を抑え肥満予防にも
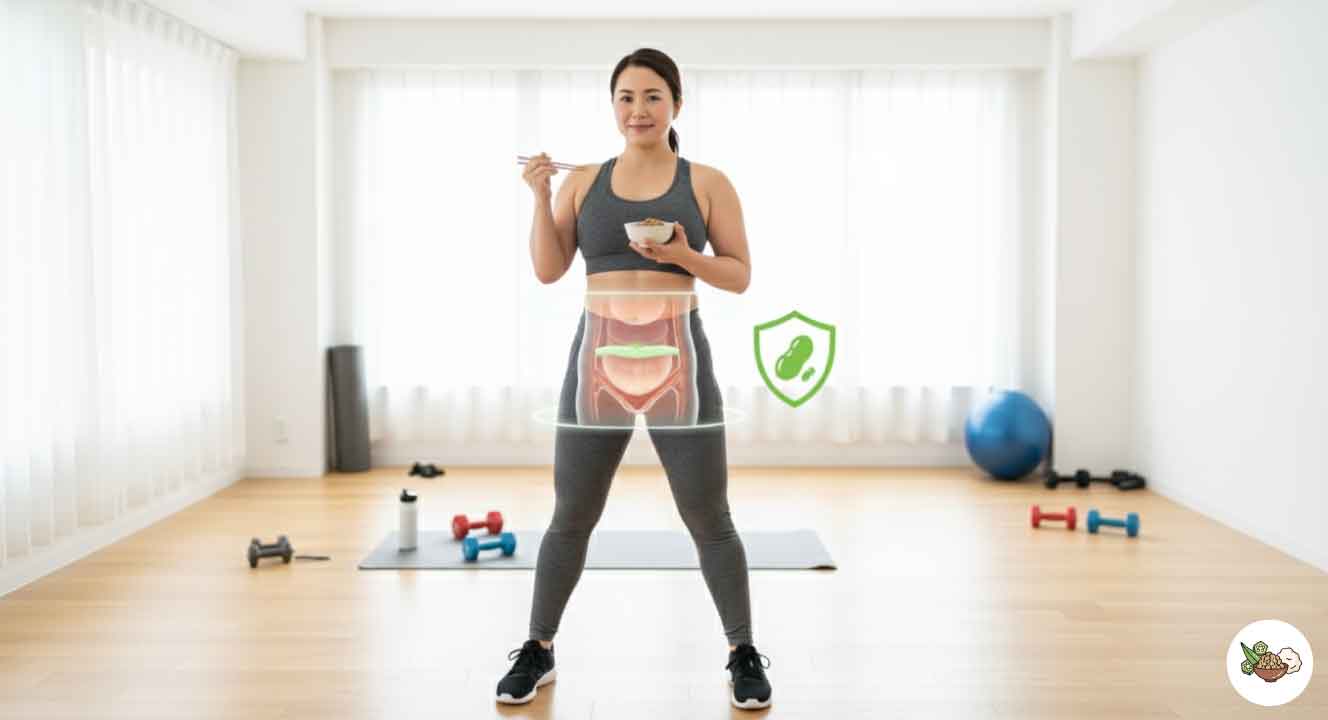
ねばねば研究所・イメージ
納豆は、単にカロリーが低いだけでなく、体脂肪、特に「内臓脂肪」の蓄積を抑える可能性を秘めた成分を含んでいます。
その成分とは、納豆の原料である大豆に含まれるたんぱく質の一種、「β-コングリシニン(ベータコングリシニン)」です。近年の研究により、このβ-コングリシニンには、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えたり、脂肪の蓄積を抑制したりする働きがあることが報告されています。(※1)
内臓脂肪は、皮下脂肪と比べて生活習慣病との関連が深く、健康上のリスクが高いとされています。
ダイエットの目的が体重を減らすことだけでなく、健康診断の数値を改善することや、ぽっこりお腹を解消することである場合、内臓脂肪へのアプローチは不可欠です。
おやつとして糖質や脂質の多いスナック菓子を食べる習慣を、納豆に置き換えることは、肥満予防の観点から非常に効果的です。
カロリー摂取を抑えられるだけでなく、β-コングリシニンのような成分が、積極的に脂肪の蓄積を防ぐ方向に働いてくれる可能性が期待できます。
ポイント
かつてテレビ番組の影響で「納豆ダイエット」がブームになりましたが、その際は「納豆さえ食べていれば痩せる」といった誤解が広まりました。
これは「単品ダイエット」と呼ばれる危険な方法です。
納豆は素晴らしい食品ですが、納豆だけを食べ続けると栄養が偏り、逆に健康を害する恐れがあります。
また、脂質も含まれるため、ご飯はそのままに納豆を「追加」し続ければ、当然カロリーオーバーで太る原因になります。
ここでお勧めしているのは、あくまで「おやつの代わり」として、高カロリーな間食を納豆に置き換えることです。
これにより、1日の総摂取カロリーを抑えつつ、肥満予防に役立つ成分を賢く取り入れることができます。
(※1S)参照:河村幸雄『発酵食品としての大豆の健康機能性』, J-STAGE日本醸造協会誌, 2000 年 95 巻 6 号 p. 386-394
納豆をおやつ代わりに食べる注意点と工夫
栄養面と健康・美容への抗酸化作用

ねばねば研究所・イメージ
納豆は、ダイエットや腸活だけでなく、健康維持と美容の観点からも非常に優れた栄養面を持っています。
特に注目すべきは、大豆由来の「抗酸化作用」を持つ成分です。
私たちの体は、呼吸によって取り入れた酸素の一部が「活性酸素」に変化します。
適度な活性酸素はウイルス撃退などに役立ちますが、増えすぎると細胞を傷つけ、老化や生活習慣病の原因となると言われています。
この活性酸素の働きを抑えるのが「抗酸化作用」です。
1. 大豆サポニン
大豆の苦味やえぐみの成分である「サポニン」には、強い抗酸化作用があるとされています。
これにより、体のサビつきを防ぎ、若々しさを保つアンチエイジング効果が期待できます。
また、サポニンには脂質の蓄積を抑える働きも報告されており、肥満予防の面でもサポート役となります。
2. 大豆イソフラボン
納豆に含まれるポリフェノールの一種である「大豆イソフラボン」も、強力な抗酸化物質です。
しかし、イソフラボンの最も注目される働きは、女性ホルモン「エストロゲン」と似た構造を持ち、同様の働きをする点にあります。
エストロゲンは、女性の美しさや若々しさを保つために不可欠なホルモンですが、年齢とともに分泌量が減少します。
イソフラボンは、この減少するエストロゲンの働きを補い、以下のような美容・健康効果が期待できます。
- 美肌効果:肌のハリを保つコラーゲンの生成を助け、肌の新陳代謝を促します。
- 骨粗しょう症予防:骨からカルシウムが溶け出すのを防ぎ、骨密度を維持するのを助けます。
- PMS(月経前症候群)の緩和:ホルモンバランスの乱れによる不調を和らげる可能性が報告されています。
ダイエット中は食事制限によって肌荒れや体調不良が起こりやすいですが、おやつに納豆を取り入れることで、抗酸化作用とイソフラボンの力で、内側から健康と美容をサポートすることができます。
発酵食品特有のビタミンとアミノ酸

ねばねば研究所・イメージ
納豆の栄養価の高さは、大豆そのものが持つ力に加え、「発酵」のプロセスによって生まれる栄養素によるところが大きいです。
納豆菌が大豆を分解・発酵させる過程で、元の煮大豆には少なかった、あるいは含まれていなかった発酵食品特有のビタミンやアミノ酸が豊富に生成されます。
1. エネルギー代謝を助ける「ビタミンB2」
納豆にはビタミンB群が豊富ですが、特に含有量が多いのが「ビタミンB2」です。
ビタミンB2は「脂質の代謝」に不可欠な栄養素で、摂取した脂質を分解してエネルギーに変換する際のサポート役(補酵素)として働きます。
ダイエット中に脂質代謝を効率よく行うために非常に重要です。
また、皮膚や粘膜の健康を保つ働きもあり、「発育のビタミン」とも呼ばれ、健康的な肌や髪を維持するためにも役立ちます。
2. 骨の健康を守る「ビタミンK」
納豆には、ビタミンKが他の食品と比較して群を抜いて多く含まれています。
ビタミンKには種類があり、納豆に豊富なのは「ビタミンK2」です。
ビタミンK2は、カルシウムが骨に沈着するのを助け、骨の形成を促す働きがあります。
骨粗しょう症の予防に重要な役割を果たします。
3. 血液サラサラの「ナットウキナーゼ」
これは栄養素ではありませんが、納豆のネバネバ部分に含まれる特有の酵素が「ナットウキナーゼ」です。
ナットウキナーゼには、血栓(血の塊)を溶かす働きがあるとされ、血液をサラサラに保つのに役立つと注目されています。
ただし、ナットウキナーゼは熱に弱く、70℃以上で活性が失われるため、加熱しすぎない食べ方が推奨されます。
4. 良質なたんぱく質「アミノ酸」
前述の通り納豆は高たんぱく質ですが、その「質」も非常に高いのが特徴です。
たんぱく質の質は、体内で合成できない「必須アミノ酸」がどれだけバランス良く含まれているかを示す「アミノ酸スコア」で評価されます。
納豆(大豆)のアミノ酸スコアは100(満点)であり、肉や卵に匹敵する良質なたんぱく質源です。
発酵によりアミノ酸が分解され、吸収されやすい形になっているのもメリットです。
粒とひきわり納豆の栄養の違い
スーパーの納豆売り場には、豆の形がそのままの「粒納豆」と、豆を砕いた「ひきわり納豆」があります。
これらは単に食感が違うだけでなく、製法が異なるため栄養価にも違いが生じます。
- 粒納豆:大豆を丸ごと浸水させ、蒸してから納豆菌を付けて発酵させたもの。
- ひきわり納豆:大豆をまず細かく砕き(引き割り)、皮を取り除いてから浸水させ、蒸して納豆菌を付けて発酵させたもの。
この製法の違いが、栄養素に以下のような差をもたらします。
1. 食物繊維は「粒納豆」が豊富
ひきわり納豆は製造工程で大豆の「皮」を取り除きます。
大豆の皮には不溶性食物繊維が豊富に含まれているため、皮ごと食べられる粒納豆の方が、食物繊維の総量は多くなります。
便秘解消効果をより重視する場合は、粒納豆がおすすめです。
2. ビタミンKは「ひきわり納豆」が豊富
ひきわり納豆は、大豆を砕いてから納豆菌を付着させます。
そのため、丸ごとの大豆よりも表面積が広くなり、納豆菌がより活発に働くことができます。
この結果、納豆菌が生成するビタミンK(特にK2)の含有量は、ひきわり納豆の方が粒納豆よりも多くなる傾向があります。
骨の健康を特に意識する場合は、ひきわり納豆が良いでしょう。
3. 消化吸収は「ひきわり納豆」が有利
ひきわり納豆は皮がなく、あらかじめ砕かれているため、粒納豆に比べて消化吸収が良いとされています。
胃腸が弱い方や、小さなお子さん、ご高齢の方にはひきわり納豆が適している場合があります。
栄養価の比較(1パック50gあたり推定値)
| 栄養素 | 粒納豆(糸引き納豆) | ひきわり納豆 | 主な働き・特徴 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 約92kcal | 約93kcal | ほぼ差はない |
| たんぱく質 | 約8.3g | 約8.3g | ほぼ差はない |
| 食物繊維 | 約4.8g | 約3.0g | 皮を含む粒納豆が多い |
| ビタミンK | 約440μg | 約470μg | 発酵面積が広いひきわりが多い |
| カルシウム | 約46mg | 約30mg | 皮やその周辺に含まれるため粒が多い |
| 大豆イソフラボン | 約37mg | 約37mg | ほぼ差はない |
※数値は「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」等のデータを基にした50g換算の目安です。
目的に合わせた選び方
- 整腸作用・便秘解消を重視=粒納豆(食物繊維が豊富)
- 骨の健康・骨粗しょう症予防を重視=ひきわり納豆(ビタミンKが豊富)
- 消化の良さを重視=ひきわり納豆
どちらも優れた食品であることに変わりはないため、最終的には食感の好みで選んでも問題ありません。
おやつとして飽きないよう、日替わりで変えてみるのも良いでしょう。
プリン体に注意しレシピも工夫

ねばねば研究所・イメージ
多くの健康・美容メリットがある納豆ですが、おやつとして習慣的に食べる際には、いくつか注意すべき点もあります。
また、毎日同じ食べ方では飽きてしまうため、簡単なレシピの工夫も重要です。
注意点1:食べ過ぎによるカロリー・脂質オーバー
納豆は低カロリーとはいえ、ゼロカロリーではありません。
1パック(50g)で約90kcal、脂質も約5g含まれています。
これは良質な脂質ですが、1日に何パックも食べれば、当然カロリーオーバーとなり太る原因になります。
おやつとしての摂取は、他の食事とのバランスを考え、1日に1〜2パック程度を目安にするのが賢明です。
注意点2:プリン体の含有量
納豆は大豆製品であり、細胞数が多いため「プリン体」を比較的多く含みます。
プリン体は体内で代謝されて「尿酸」になりますが、尿酸が過剰になると高尿酸血症や痛風の原因となる可能性があります。
プリン体の摂取量に注意
納豆1パック(50g)には約57mgのプリン体が含まれるとされています。
高尿酸血症・痛風のガイドラインでは、プリン体の1日の摂取目安を400mgとしています。
納豆だけが突出して高いわけではありませんが(鶏レバー100gで約312mg)、他の食事(肉や魚介類、ビールなど)にもプリン体は含まれるため、既に尿酸値が高い方や治療中の方は、食べ過ぎに注意が必要です。
(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット「プリン体」)
注意点3:タレによる塩分・糖分
付属のタレは美味しく食べやすいですが、意外と塩分や糖分(果糖ぶどう糖液糖など)が含まれています。
おやつとして食べる際は、タレを使わずに食べる工夫も、ダイエットや健康管理の面で有効です。
おやつ向けのおすすめレシピ・工夫
毎日飽きずにおやつとして納豆を楽しむための、簡単なアレンジをご紹介します。
- タレなし+薬味(医師も実践):タレの代わりに、鰹節、刻み海苔、生姜(すりおろし)、七味唐辛子、ごま油などを少量加える。これらはコンビニやスーパーで手軽に入手できます。特に鰹節の旨味や生姜の辛味は、タレがなくても納豆の味を引き立てます。
- 豆腐と合わせる(満腹感アップ):納豆1パックと、小さいパックの豆腐(絹でも木綿でも)を混ぜる。どちらも低糖質・高たんぱくで、ボリュームが格段にアップします。味付けは同様に薬味や、少量のポン酢でも良いでしょう。
- ケーキ納豆(マヨネーズ少量):前述の通り、混ぜずにスプーンですくって食べる方法です。この食べ方を紹介する医師は、少量のマヨネーズをかけることを推奨しています。マヨネーズはカロリーが高いですが糖質は少ないため、少量であれば問題ないという考え方です。
- 納豆トースト(満足感):食パンに納豆、ツナ缶(ノンオイル)、チーズなどを乗せてトーストします。手軽に作れて満足感が高く、軽食にもなります。ナットウキナーゼは熱に弱いため、焼きすぎには注意しましょう。
- 加工品の活用(手軽さ):フリーズドライ加工された「納豆スナック」や、味付けされた「おつまみ納豆」も市販されています。これらは手を汚さずにつまめる手軽さが魅力です。ただし、油で揚げている製品や、塩分・糖分が多い製品もあるため、購入時には栄養成分表示を確認しましょう。
賢く納豆をおやつ代わりに活用
納豆をおやつ代わりにすることについて、そのメリットや注意点を解説してきました。
最後に、この記事の要点をリストでまとめます。
まとめ
- 納豆はダイエット中の間食に適している
- 1パック約80〜90kcalと低カロリー
- たんぱく質が豊富で筋肉維持をサポート
- 糖質が1パック約2.5gと非常に少ない
- 低糖質で食後の血糖値の急上昇を抑える
- 食物繊維とたんぱく質で満腹感が続き腹持ちがいい
- 食物繊維は便秘解消のサポートに役立つ
- 納豆菌は生きて腸に届きやすく腸内環境を整える
- 腸を整えることは免疫力の向上にも繋がる
- 大豆たんぱく質が内臓脂肪の蓄積を抑える可能性
- サポニンやイソフラボンが健康と美容をサポート
- 発酵によりビタミンB2やビタミンKが豊富
- 粒納豆は食物繊維、ひきわり納豆はビタミンKが多い
- プリン体を含むため1日1〜2パックが目安
- タレなしで薬味を活用するなどレシピも工夫できる
納豆をおやつ代わりに活用するメリットと注意点をご紹介しました。
納豆は低糖質・高たんぱくで腹持ちが良く、ダイエット中の間食に最適です。
食物繊維による便秘解消サポートや、納豆菌による腸活、イソフラボンによる美容効果まで期待できるのは大きな魅力です。
ただし、プリン体や脂質も含むため、1日1〜2パックを目安にすることが大切です。
タレを使わずに薬味を変えたり、豆腐と合わせたりする簡単な工夫で、飽きずに続けられます。
賢く納豆を取り入れ、我慢しない健康的なダイエットを実現しましょう。