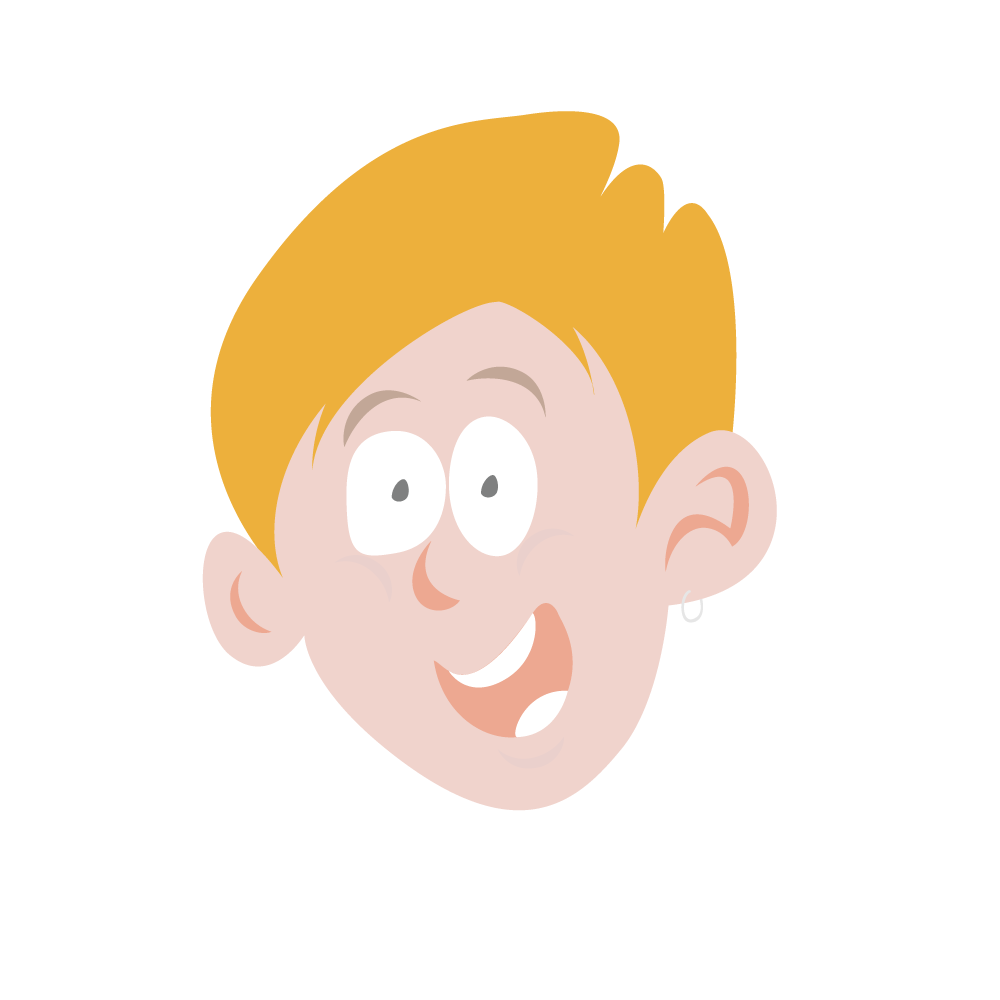ねばねば研究所・イメージ
とろろを食べた時のピリピリする不快感。
その原因と対策、そして食べても大丈夫なのか気になりますよね。
この記事では、傷んでいる山芋の特徴とおいしい山芋の特徴の見分け方、山芋の状態別の賞味期限や長持ちさせる保存のコツ、さらには山芋が持つ健康へのメリットまで解説します。
また、調理時の手の「かゆみ」の原因と、その対策についても詳しくご紹介します。
ポイント
- とろろがピリピリする2つの主な原因
- ピリピリした時の具体的な対策と予防法
- 新鮮な山芋の選び方と正しい保存方法
- 調理時の「かゆみ」の原因と対処法
とろろがピリピリする!その原因とは
ピリピリする2つの主な原因

ねばねば研究所・イメージ
とろろご飯や山かけそばを食べた時、舌や喉が「ピリピリ」「チクチク」と感じる不快な刺激。
これには、主に2つの原因が考えられます。
どちらも山芋が本来持つ成分や特性によるものであり、必ずしも「腐っている」というわけではありません。
原因1:炭酸ガス(特に真空パック品)
第一の原因は、山芋の「呼吸」によって発生する炭酸ガスです。
山芋は収穫された後も生きており、呼吸を続けています。
特に、洗浄されてカットされた山芋を真空パック詰めすると、密閉された袋の中で山芋の呼吸が続きます。
この呼吸によって排出された炭酸ガスが、パック内にどんどん溜まっていきます。
特に、貯蔵期間が長くなったり、常温に近いなど保存温度が高かったりすると、山芋の呼吸活動はさらに活発になり、多くの炭酸ガスを発生させます。
この高濃度に溜まった炭酸ガスが、開封して食べた際に舌の粘膜を強く刺激し、酸味や辛味、まるで炭酸水のようなピリピリとした刺激として感じられるのです。
パックがパンパンに膨らんでいなくても、ガスが充満しているケースは多々あります。
原因2:シュウ酸カルシウム(生食時の刺激)
もう一つの主要な原因は、山芋自体が含有する「シュウ酸カルシウム」という成分です。
これはアクの一種であり、目には見えないほど微細な「針状結晶(しんじょうけっしょう)」の形をしています。
この針状の結晶が、とろろを食べた際に口の中や喉の粘膜に物理的に突き刺さることが、チクチクとした刺激やピリピリ感の正体です。
このシュウ酸カルシウムは、特に山芋の皮のすぐ下に多く含まれています。
これは山芋が外敵から身を守るための生体防御機能の一つとも言われており、山芋の鮮度や保存状態に関わらず、生で食べれば誰もが感じる可能性のある刺激です。
特に粘りが強くアクも強いとされる大和芋や自然薯は、長芋に比べてこの刺激を強く感じやすい傾向があります。
原因の見分け方(目安)
・真空パック品で特に強く感じる、酸味も伴う → 炭酸ガスの可能性大
・生の山芋をすりおろした直後から感じる、チクチク感が強い → シュウ酸カルシウムの可能性大
ピリピリする山芋は食べても大丈夫?
ピリピリとした刺激を感じると、即座に「傷んでいるのでは?」「食中毒が怖い」と不安になるかもしれませんが、その原因によって対処は異なります。
結論として、ピリピリの原因が前述の炭酸ガスやシュウ酸カルシウムであった場合、それ自体が体に害を及ぼす毒素というわけではないため、食べることは可能とされています。
ただし、これはあくまで「安全性」の話です。
炭酸ガスが充満している山芋は、風味や味が著しく落ちており、単純に「美味しくない」状態です。
また、シュウ酸カルシウムによる刺激も、強すぎると食事の妨げになります。
ポイント
最も注意すべきは、ピリピリの原因がガスや結晶ではなく「腐敗」である場合です。
細菌が繁殖して発生するピリピリ感や酸味は非常に危険です。
以下の特徴が見られたら、食べるのは絶対にやめてください。
- 明らかな異臭:酸っぱい臭い(酢酸臭)、アンモニア臭、アルコールのような発酵臭など、山芋本来の土の香りとは異なる刺激臭がする。
- 強い酸味や苦味:ピリピリ感だけでなく、味覚として明らかな「酸っぱさ」や「苦さ」を感じる。
- 異常な粘り・溶け:全体がドロドロに溶けていたり、糸を引く粘りが異常に強くなっていたりする。
- カビの発生:表面や切り口に、白、青、黒などのフワフワしたカビが生えている。
- 変色:ピンク色を通り越して、広範囲が茶色や黒に変色し、水分が滲み出ている。
これらのサインは、腐敗が進行している証拠です。
少しでも「いつもと違う」「おかしい」と感じたら、無理に食べずに廃棄する勇気を持ちましょう。
ピリピリ感をなくすための対策

ねばねば研究所・イメージ
ピリピリの原因が腐敗ではなく、炭酸ガスやシュウ酸カルシウムであると判断できた場合、いくつかの簡単な対策で刺激を和らげ、美味しく食べることが可能です。
炭酸ガスが原因の場合の対策
真空パック品がピリピリする場合、溜まったガスを逃がすことが最も有効です。
- 空気にさらす(ガス抜き):最も簡単な方法です。パックから山芋(またはとろろ)をボウルなどに出し、ラップをせずに冷蔵庫で2時間程度放置します。空気にさらすことで、組織に溶け込んでいた炭酸ガスが抜けていき、刺激が和らぎます。
- 加熱調理する:炭酸ガスは加熱によって完全に飛びます。ピリピリ感が強い場合は、生食を諦め、加熱調理に切り替えるのが確実です。とろろ焼き、お好み焼きのつなぎ、スープの具材(すいとんのように)などで活用しましょう。
シュウ酸カルシウムが原因の場合の対策
針状結晶による物理的な刺激は、「酸」または「熱」によってその性質を変えさせることで緩和できます。
- 酢を加える:シュウ酸カルシウムは酸に弱い性質があります。すりおろしたとろろに少量の酢(とろろ100gに対し、小さじ1/2程度が目安)を加えてよく混ぜると、結晶の構造が変化し、刺激がマイルドになります。変色防止にも役立ちます。
- 加熱調理する:シュウ酸カルシウムも熱に弱いとされています。加熱することで結晶が変性・分解されるため、刺激を感じなくなります。ソテーや煮物などに使用すれば、ピリピリ感を心配する必要はありません。
どちらの原因でも「加熱」が最強の対策
生で食べたい場合は「ガス抜き」や「酢を加える」といった対策がありますが、最も確実かつ簡単な対策は「加熱調理」です。
ピリピリ感が不快な場合は、無理せず加熱して美味しくいただきましょう。
手の「かゆみ」を引き起こす原因
山芋を調理する上で、ピリピリ感と同じくらい厄介なのが、皮をむいたり、すりおろしたりする際の「手の激しいかゆみ」です。
このかゆみの原因も、とろろを食べた時のピリピリ感(原因2)と同じ、「シュウ酸カルシウム」の針状結晶です。
山芋の皮をむいたり、特におろし金ですりおろしたりする行為は、皮の近くに大量に存在するシュウ酸カルシウムの結晶を砕き、皮膚の表面に擦り付けることになります。
その結果、無数のミクロな針が手の皮膚(特に指紋やシワの間)に突き刺さり、物理的な刺激となって激しいかゆみやムズムズ感を引き起こすのです。
手が濡れていると、結晶が皮膚に付着しやすくなるため、かゆみが増すとも言われています。
かゆみ=アレルギーではない?
このかゆみは、シュウ酸カルシウムという物質による物理的な刺激が原因です。
そのため、ヒスタミンが関与するような一般的な食物アレルギー反応(免疫反応)とはメカニズムが異なります。
かゆみだけが出ているのであれば、アレルギーではない可能性が高いです。
ただし、ごく稀に山芋自体(タンパク質)にアレルギーを持つ方もいます。
もし、食べた後に蕁麻疹(じんましん)、呼吸困難、腹痛、胃痛など、皮膚のかゆみ以外の重い症状が出た場合は、アレルギーの可能性も否定できません。
その際は速やかに医療機関を受診してください。
調理中のかゆみ対策と予防法

ねばねば研究所・イメージ
一度かゆくなると、調理に集中できなくなるほど辛い山芋のかゆみ。
しかし、適切な「予防法」と「対処法」を知っておけば、恐れることはありません。
かゆみを防ぐ「予防法」
最も重要なのは、かゆくなる前に対策することです。
- 調理用手袋を着用する:最も確実で簡単な方法です。物理的に結晶が手に触れるのを防ぎます。
- 手に酢水をつける:調理を始める前に、手を酢水(水200mlに酢大さじ1程度が目安)で湿らせておきます。シュウ酸カルシウムは酸に弱いため、結晶の働きを弱め、かゆみを予防する効果が期待できます。
- 皮を厚めに剥く:前述の通り、かゆみの原因物質は皮の周辺に集中しています。ピーラーなどで2〜3mm程度、いつもより厚めに皮を剥くことで、手に付着する結晶の量を大幅に減らせます。
- 冷凍してからすりおろす:皮を剥いた山芋をラップに包み、一度冷凍します。凍ったまま(または半解凍で)すりおろすと、冷凍によって結晶が折れやすくなっているため、かゆみを感じにくくなると言われています。ただし、非常に冷たいので布巾などで持って作業しましょう。
かゆくなってしまった時の「対処法」
もし予防を忘れてかゆくなってしまった場合は、慌てずに以下の方法を試してください。
(※手でこすったり掻いたりすると、結晶がさらに深く刺さるので厳禁です)
- 酢水で洗う:かゆみの予防にも使った「酢」が有効です。かゆい部分に直接酢をつけて軽く揉み込むか、酢水で手を丁寧に洗い流します。指に傷があると染みることがあるので注意してください。
- お湯で洗う:シュウ酸カルシウムは熱にも弱い性質があります。40度〜45度程度の、火傷しない範囲で少し熱めのお湯で手を洗い流します。結晶が分解・変性しやすくなり、かゆみが急速に収まることが期待できます。山芋のヌメリも同時に取れやすくなるのでおすすめです。
- 米で擦る(民間療法):乾いた手で米びつの「生米」を掴み、手のひらや指を擦り合わせるように揉むと、米の粒子が皮膚に刺さった結晶を掻き出してくれる、という民間療法もあります。ただし、皮膚が弱い方は刺激になる可能性もあるため、注意が必要です。
おすすめは「お湯」
いくつかの方法がありますが、最も即効性を感じやすく、家庭で準備しやすいのは「お湯で洗う」方法です。
かゆみとヌメリが同時に取れてスッキリします。
ただし、冬場は手が乾燥しやすいので、洗い終わったらすぐにハンドクリームで保湿ケアをしましょう。
とろろのピリピリを防ぐ山芋の選び方
新鮮でおいしい山芋の特徴

ねばねば研究所・イメージ
ピリピリ感を避け、美味しく食べるためには、購入時にできるだけ新鮮な山芋を選ぶことが基本です。
以下のポイントをチェックして、良質な山芋を見分けましょう。
- ずっしりとした重みがある:手に持った時に、見た目の太さや長さ以上に重く感じるものは、水分が豊富に詰まっている証拠です。みずみずしく、美味しい山芋です。
- 表面が滑らかで傷が少ない:皮の凹凸が少なく、傷や黒ずんだ斑点がないものが良品です。表面がきれいなものは、生育環境が良く、丁寧に扱われた証拠です。
- 太さが均等である:端から端まで、なるべく均一な太さのものが望ましいです。部分的に細すぎると、その部分だけ早く乾燥しやすくなります。
- 断面が真っ白でみずみずしい(カット品の場合):スーパーでよく見かけるカットされた山芋は、切り口が勝負です。酸化が進んでいない、雪のように真っ白で、水分が滲み出ているようなみずみずしいものを選びましょう。茶色や赤っぽく変色しているものは、カットされてから時間が経過しており、鮮度が落ちています。
- 皮が適度に湿っている:カサカサに乾燥しているものより、適度な湿り気を感じるほうが新鮮です。
- ヒゲ根が少ない(または多い):ヒゲ根の処理が面倒な場合は、少ないものが調理しやすいです。一方で、一般的に「ヒゲ根やその跡が多いものほど粘りが強い」とも言われているため、とろろの粘りを重視するなら、あえてヒゲ根が多いものを選ぶのも一つの方法です。
「おがくず入り」や「真空パック」も賢い選択
おがくずに埋められて売られている山芋は、おがくずが天然の保湿・調湿材となり、乾燥や過度な湿気から山芋を守ってくれるため、日持ちしやすい傾向があります。
また、すぐに使わない場合は、未開封時の賞味期限が比較的長い真空パック品を選ぶのも合理的です。
(ただし、購入後はピリピリ対策で早めに開封するか、冷蔵保存を徹底しましょう)
傷んでいる山芋の特徴とは?
ピリピリ感と「腐敗」は別問題であると解説しましたが、もちろん山芋も生鮮食品であり、時間と共に傷んでいきます。
新鮮な山芋を選び、傷んだものを避けるための見分け方を覚えましょう。
以下のような特徴が見られたら、腐敗や劣化が進んでいるサインです。
食べるのを避けるか、傷んだ部分を大きく(最低でも周囲1〜2cmを含めて)取り除いてください。
- 異臭がする:前述の通り、酸っぱい臭い(酢酸臭)、アルコールのような発酵臭、アンモニア臭など、土の香りとは明らかに異なる不快な臭いがする場合は、細菌による腐敗が始まっています。
- カビが生えている:表面に白や青、黒などのフワフワしたカビが生えているもの。部分的に生えているだけでも、菌糸が内部深くまで伸びている可能性があるため、廃棄するのが最も安全です。
- 柔らかくなっている:指で押すとブヨブヨと柔らかい感触がある場合、内部の組織が壊れ、腐敗や発酵が進んでいます。
- ドロドロになっている部分がある:カットした際、中が溶けていたり、水っぽくドロドロになっていたりする部分は、腐敗しています。
- 断面がひどく変色している:カット品で、断面が広範囲にわたって茶色や黒に変色しているものは、酸化が進み、風味が著しく落ちています。
- 乾燥して萎びている:皮がシワシワになり、水分が抜けきって軽くなっているもの。風味や食感が悪くなっています。
断面が「ピンク色」になるのは腐敗ではない!
山芋をカットしたり、すりおろしたりして放置すると、断面が「ピンク色」に変色することがあります。
これは腐敗ではなく、食べても問題ありません。
山芋に含まれるポリフェノール類が、チロシナーゼなどの酸化酵素と反応して起こる自然な現象です。
しかし、これは酸化が始まっているサインであり、そのまま放置するとピンク色から褐色(茶色)に変化し、味や風味が落ち、苦みや渋みの原因にもなります。
ピンク色になったら、それ以上酸化が進む前に早めに使い切りましょう。
山芋の状態別の賞味期限目安
山芋の賞味期限は、保存状態によって劇的に変わります。
特に「カットする」「すりおろす」という行為は、酸化を急激に進めるため、日持ちしなくなります。
以下に、状態別の一般的な保存期間の目安を示します。
| 山芋の状態 | 保存方法 | 賞味期限の目安 | 日持ちしない理由 |
|---|---|---|---|
| 1本丸ごと(土付き) | 冷暗所(常温) | 約1か月(寒い時期) | 皮が全体を保護し、土が湿度を保つため。 |
| カットされた山芋 | 冷蔵(野菜室) | 約1週間 | 切り口から酸化と水分の蒸発が急速に進むため。 |
| すりおろした山芋(とろろ) | 冷蔵 | 約2日(常温なら当日) | 空気に触れる面積が最大になり、酸化が最も早いため。 |
| 真空パック(未開封) | 冷蔵 | 約2週間 | 空気が遮断され酸化は防げるが、呼吸は続くため。 |
| 冷凍保存(全般) | 冷凍 | 約1か月 | 風味や食感は落ちるが、腐敗は防げるため。 |
最も注意すべきは、すりおろした状態(とろろ)です。
空気に触れる面積が爆発的に増えるため、酸化酵素が一気に活性化します。
冷蔵保存していても、味や風味はどんどん落ちていくため、2日以内には食べきるようにしましょう。
ちなみに、市販されているパック詰めの冷凍とろろ製品は、急速冷凍技術やpH調整剤(変色防止)の使用などにより、家庭での手作りとろろよりも長く日持ちするよう設計されています。
| 商品例 | 保存方法 | 賞味期限の目安 |
|---|---|---|
| セブンイレブン「山芋とろろ」 | 冷凍(-18℃以下) | 製造日より1年 |
| イオン「国産原料使用大和芋入りとろろ」 | 冷凍(-18℃以下) | 製造日より18か月後 |
| マルハチ「とろろ3個パック」 | 冷蔵(0~10℃) | 12日 |
※市販品の賞味期限は非常に長期間ですが、これは製造技術によるものです。家庭で調理した場合は、上記の「手作り」の目安に従ってください。また、購入時は必ず商品の表示をご確認ください。
長持ちさせる保存のコツ

ねばねば研究所・イメージ
山芋を美味しく長持ちさせるための最大の敵は、「乾燥」と「酸化」です。
これをいかに防ぐかが、保存の鍵となります。
常温で保存する場合(1本丸ごと)
土付きの山芋が1本丸ごと手に入った場合、寒い時期(冬場など)であれば常温保存が可能です。
山芋は乾燥と光に弱いため、新聞紙やキッチンペーパーで包み、風通しのよい冷暗所(例:暖房の影響がない廊下やパントリー)で保存します。
新聞紙で包むのは、適度な湿度を保ちつつ、山芋の呼吸を妨げない(密閉しない)ためです。
暖かい時期(春〜夏)は、常温では傷みやすくなるため、丸ごとであっても冷蔵保存に切り替えましょう。
冷蔵保存する場合(丸ごと・カット・とろろ)
暖かい時期や、使いかけの山芋は、冷蔵庫の野菜室が基本です。
- 丸ごとの場合:常温と同様に新聞紙などで包み、乾燥を防ぐためにポリ袋に入れて、口を軽く閉じて野菜室で保存します。
- カットした場合:切り口の酸化と乾燥を徹底的に防ぐことが最重要です。切り口に酢を薄く塗ると変色防止になります。その後、切り口をキッチンペーパーで覆い、その上からラップで隙間なくぴったりと包みます。最後に密閉袋やポリ袋に入れて野菜室で保存します。
- すりおろした場合(とろろ):酸化が非常に早いため、おすすめはしませんが、保存する場合は密閉容器に入れます。空気に触れる面積を減らすため、表面を平らにならしてからラップを密着させ、フタをします。前述の通り、少量の酢を混ぜておくと変色防止に役立ちますが、それでも2日以内に食べきりましょう。
冷凍保存する場合(最もおすすめ)
すぐに使い切れない場合、冷凍保存が最も合理的です。
約1か月間保存可能になります。
ただし、山芋は冷凍すると水分が抜けて食感が変わりやすいため、丸ごと冷凍するのは絶対に避けてください。
以下の状態で加工してから冷凍するのがおすすめです。
- すりおろして(とろろ):フリーザーパック(ジップロックなど)にすりおろしたとろろを入れ、薄く平らにならします。こうすることで急速に凍り、解凍ムラも防げます。空気をしっかり抜いて冷凍庫へ。使う時は必要な分だけパキッと折って解凍できるので非常に便利です。
- カットして(短冊切り・輪切りなど):調理しやすい形(短冊切り、輪切り、乱切りなど)にカットします。変色を防ぐため、酢水(水400mlに対し酢小さじ1〜2杯程度)に5〜10分ほどさらします。その後、水気をキッチンペーパーでしっかり拭き取り、フリーザーパックに入れて冷凍します。
解凍方法
風味を損なわないよう、流水解凍または自然解凍(冷蔵庫内)が基本です。
時間がない場合のみ、電子レンジの「解凍機能」を使いますが、「加熱」ボタンは絶対押さないでください。
火が通ると食感がパサパサになってしまいます。
山芋の健康メリットと栄養

ねばねば研究所・イメージ
山芋(長芋、大和芋、自然薯などの総称)は、「山のうなぎ」とも呼ばれ、古くから滋養強壮に良い食材として親しまれてきました。
その栄養価について、YMYL領域(健康・医療情報)に最大限配慮し、一般的に知られている情報や公的機関の情報を基にご紹介します。
免責事項
本セクションで紹介する内容は、山芋の一般的な栄養成分に関する情報であり、特定の健康効果や効能を保証するものではありません。
山芋は食品であり、医薬品ではありません。
体調に関して不安がある場合は、医療機関にご相談ください。
山芋が持つとされる代表的な栄養成分は以下の通りです。
アミラーゼ(ジアスターゼ)
山芋の特筆すべき成分として、デンプンの分解酵素であるアミラーゼ(ジアスターゼ)が豊富に含まれているとされています。
これは大根などにも含まれる消化酵素で、炭水化物(デンプン)の消化を助ける働きが期待されています。
ご飯(デンプン)と一緒に食べる「とろろご飯」は、栄養面でも消化面でも理にかなった食べ合わせと言われることがあります。
ただし、アミラーゼは熱に非常に弱く、60度程度の加熱で失活し始めると言われています。
そのため、この消化酵素の働きを期待する場合は、加熱せずに「生」で(とろろなどで)食べるのが適しているようです。
ムチン(ネバネバ成分)
山芋やオクラ、納豆などのネバネバの正体の一つが、ムチンと呼ばれる水溶性食物繊維の一種(タンパク質と糖が結合した複合体)とされています。
ムチンには、胃腸の粘膜を保護し、潤いを保つ働きや、タンパク質の分解・吸収を助ける働きが期待されています。
このため、胃が弱っている時や、疲労時にも食べやすい食材とされています。
その他の栄養素
ほかにも、健康維持に関連する以下のような栄養素が含まれているという情報があります。
- カリウム:体内の余分なナトリウム(塩分)を排出するのを助けるミネラルとして知られています。
- ビタミンB群:エネルギー代謝を助ける補酵素として働くビタミンB1やB6などが含まれています。
- 食物繊維:ネバネバ成分の水溶性食物繊維だけでなく、不溶性食物繊維も含まれており、腸内環境のサポートが期待されます。
農林水産省の広報誌においても、山芋の消化酵素(アミラーゼ)について触れられており、その栄養的特徴が紹介されています。
(参照:農林水産省 広報誌「aff(あふ)」2011年9月号)
これらの情報から、山芋は消化を助け、胃腸を保護する働きが期待できるため、食欲がない時や夏バテ時、疲労回復をサポートしたい時などに取り入れやすい食材であると言えそうです。
とろろのピリピリを防いで美味しく
とろろがピリピリする原因や対策、山芋の保存法について解説しました。
最後に、この記事の要点をリストでまとめます。
まとめ
- とろろがピリピリする原因は主に「炭酸ガス」と「シュウ酸カルシウム」
- 炭酸ガスは真空パック品に多く、シュウ酸カルシウムは山芋自体に含まれる
- 腐敗(異臭・酸味)がなければ、ピリピリしても食べること自体に害はないとされる
- 炭酸ガスが原因の場合は味が落ちているサイン
- 炭酸ガスの対策は「空気にさらす」か「加熱する」
- シュウ酸カルシウムの対策は「酢を加える」か「加熱する」
- 調理中の手のかゆみも「シュウ酸カルシウム」が原因
- かゆみ予防には「手に酢水をつける」「皮を厚く剥く」が有効
- かゆくなったら「酢水」か「40度前後のお湯」で洗う
- 傷んだ山芋は「異臭」「カビ」「柔らかい」などの特徴がある
- 新鮮な山芋は「重みがあり」「断面が白く」「傷が少ない」
- 山芋の賞味期限は丸ごと(常温)で約1か月
- カットすると冷蔵で約1週間、すりおろすと冷蔵で約2日
- 冷凍保存ならカットやすりおろしで約1か月持つ
- 保存のコツは「乾燥」と「酸化」を防ぐこと(新聞紙やラップ)
- 山芋には消化を助けるアミラーゼなどが含まれるとされている
今回は、とろろがピリピリする原因と、調理中の不快な「かゆみ」の正体について詳しく解説しました。
原因が主に「炭酸ガス」や「シュウ酸カルシウム」であれば、加熱や酢を加えることで対策でき、腐敗のサインがなければ食べられることがお分かりいただけたかと思います。
もうピリピリを感じても、慌てて捨ててしまう必要はありません。
新鮮な山芋の選び方、正しい冷凍保存のコツ、そして調理前のかゆみ予防策を実践すれば、山芋をもっと手軽に、無駄なく食卓に取り入れられます。
この記事が、美味しいとろろ料理を安心して味わうための一助となれば幸いです。