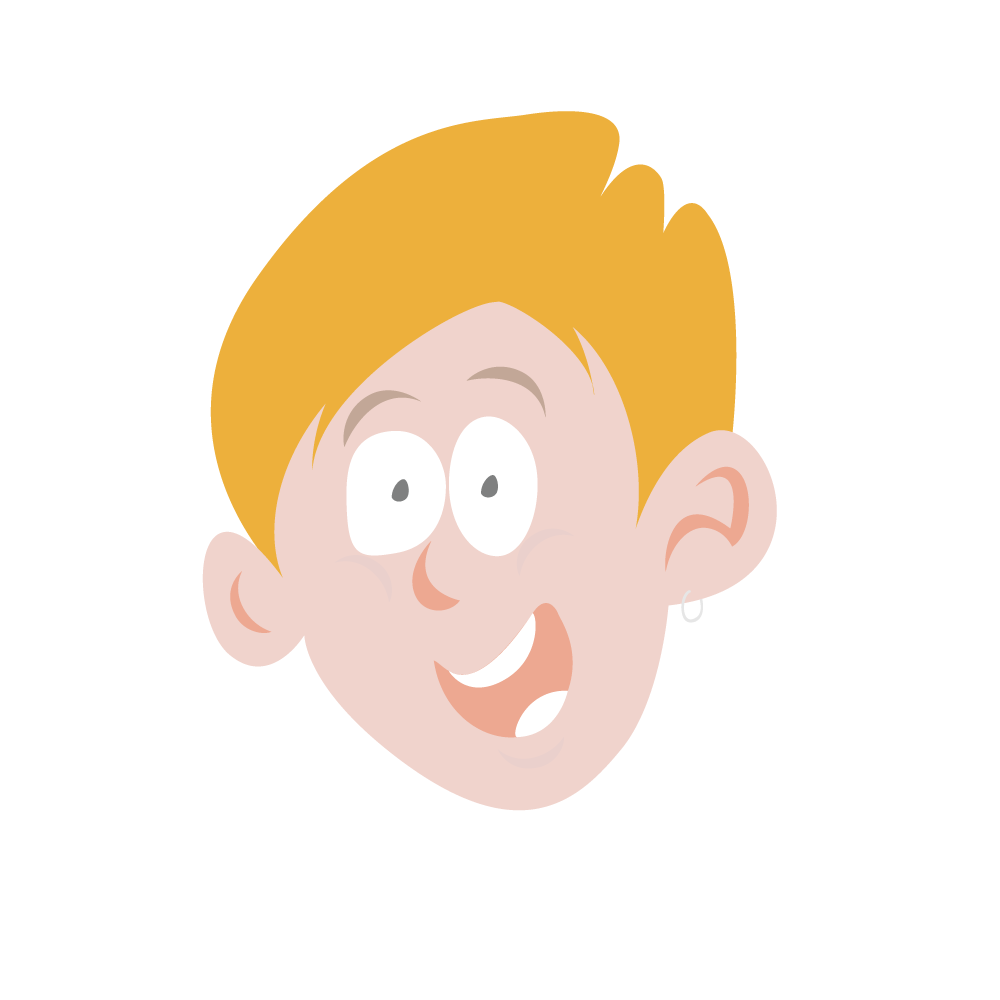ねばねば研究所・イメージ
こんにちは。ねばねば研究所、運営者の「M」です。
納豆は朝に食べるべきか、夜がいいのか、それとも朝夜両方食べた方がいいのか…
これ、納豆好きなら一度は考えるテーマですよね。すごく悩みます。
テレビやネットで「朝は腸活に良い!」と特集されたかと思えば、「いやいや、夜こそ血栓予防に効く!」なんて情報もあって、結局、納豆を食べるタイミングはどっちがいいの?って、わからなくなりがちかなと思います。
それに、もし両方のいいとこ取りをしたいなら、いっそのこと1日2パック食べてもいいのかな?なんて疑問も出てきますよね。
でも、それって食べ過ぎじゃないの?という不安もよぎります。
この記事では、そうした「納豆 朝 夜 両方」問題に関するさまざまな疑問について、栄養面での具体的な違いや、逆に食べ過ぎのリスク(特に1日2パックの場合)などを、私なりにしっかり整理してお伝えしていきますね。
注目の成分であるナットウキナーゼの効果的な時間や、納豆ダイエットはいつ食べるのがいいのか、といった気になる点にも深く触れていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
ポイント
- 朝納豆と夜納豆のメリット・デメリットの違い
- ナットウキナーゼが効果を発揮する時間帯
- 「1日2パック(朝夜両方)」が推奨されない理由
- 納豆の栄養を活かすおすすめの食べ方
納豆は朝か夜か、両方食べるべきか
日本の食卓に欠かせない納豆ですが、そのポテンシャルを最大限に引き出すタイミングはいつなんでしょうか。
「朝派」と「夜派」、それぞれの主張がありますよね。
まずは、納豆を朝か夜か、それとも両方かで、どんな違いがあるのか、基本的なところをじっくり見ていきましょう。
納豆は朝と夜どっちがいい?論争

ねばねば研究所・イメージ
昔から「納豆は朝食べるもの」というイメージが強いかもしれませんが、最近は医学的・栄養学的な観点から「夜納豆」のメリットもかなり強力にプッシュされるようになりました。
この長く続く論争、結論から言ってしまうと、「どちらも間違いなくメリットがあり、ご自身の健康目的によって最適なタイミングは異なる」というのが、私なりの答えです。
朝に食べれば、日中の活動をサポートするエネルギー源や、腸の活動(腸活)をスタートダッシュさせるのに役立つと言われています。
一方で、夜に食べれば、私たちが寝ている間の血栓予防や、身体の修復・成長をサポートするなど、夜特有の生理現象に合わせた効果が期待できるんです。
どちらも魅力的ですよね。
まずは、それぞれのメリットを比較しやすいように、簡単なテーブルにまとめてみました。
【朝納豆 vs 夜納豆】期待できる主な効果の比較
| 摂取タイミング | 主な目的 | 関連する主な栄養素 | 期待される効果 |
|---|---|---|---|
| 朝 | 日中の活動サポート (エネルギー・腸活) | たんぱく質 食物繊維・納豆菌 | ・日中の持続的エネルギー供給 ・腸の覚醒、便通改善サポート ・集中力や精神的安定への寄与 |
| 夜 | 夜間の身体修復・予防 (血栓予防・成長) | ナットウキナーゼ アルギニン トリプトファン | ・睡眠中の血栓溶解促進(最重要) ・成長ホルモンの分泌サポート ・睡眠の質向上、美肌サポート |
※これらは一般的な栄養学上の期待効果であり、個人差があります。
こうして見ると、目的が全然違いますよね。
次のセクションから、それぞれのメリットをもう少し詳しく、私なりに深掘りしていきます。
朝納豆の腸活・エネルギー効果
まずは王道、「朝納豆」のメリットですね。
日本の朝ごはんの定番というだけあって、一日のスタートを切る上で、とても理にかなっています。
良質なタンパク質の補給
納豆は「畑の肉」と呼ばれる大豆からできており、良質な植物性タンパク質が本当に豊富です。
一般的な1パック(約45g~50g)で、7.5g~8.3gものタンパク質が摂れると言われています。
朝食でタンパク質をしっかり摂ることは、体温を上昇させ、日中の活動に必要なエネルギーを持続的に供給するのに役立ちます。
筋肉の維持はもちろん、脳の働きをサポートするホルモンの材料にもなるため、活動的な一日を支える基盤になってくれるんですね。
「腸を目覚めさせる」スイッチ
私が朝納豆で一番注目しているのが、この「腸活」効果です。
朝、特に朝食を摂ることは、これから活動を始める腸を「目覚めさせる」ための重要なスイッチになります。
納豆には、生きて腸まで届きやすい強力な善玉菌である「納豆菌」と、水溶性・不溶性の両方を含む「豊富な食物繊維」が含まれています。
このコンビが、活動を開始する朝の腸内環境をダイレクトにサポートし、腸内フローラを整え、お通じのリズムを作る手助けをしてくれるんです。
腸は「第二の脳」とも称されるくらい、全身の健康と密接に関わっています。
腸内環境が整うことは、便通改善だけでなく、免疫力の維持、集中力、さらには幸福ホルモンと呼ばれる「セロトニン」の分泌にも良い影響を与えることが知られています。
朝からスッキリと、前向きな気分でスタートを切るためにも、朝納豆はすごく良い習慣かなと思います。
夜納豆の血栓予防と美肌効果
次に、最近その合理性から非常に注目されている「夜納豆」のメリットです。
こちらは、朝の摂取以上に、人体の生理学的なリズム(サーカディアンリズム)と、納豆の含有成分の作用時間が、見事に噛み合っているんです。
夜納豆の最大のメリット:血栓予防
夜納豆を推奨する最大の理由は、納豆のあのネバネバ部分に含まれる特有の酵素「ナットウキナーゼ」の効果を、最大限に発揮できる点にあります。
ナットウキナーゼには、血栓(血液の塊で、主成分はフィブリン)を直接的に溶かす(溶解する)強力な働きがあることが、多くの研究で報告されています。
一方で、私たちの身体は、生理学的に寝ている間(特に深夜から早朝)に、コップ1杯分とも言われる汗をかき、体内の水分が失われやすくなります。
その結果、血液が凝固しやすい(ドロドロになりやすい)危険な時間帯に入ると言われています。
実際に、脳梗塞や心筋梗塞といった恐ろしい血栓性の病気が、明け方に多発する傾向があるのは、このためだと考えられています。
夕食や就寝前に納豆を食べることで、この最もリスクが高まる「深夜~早朝」の時間帯に、ナットウキナーゼの血栓溶解パワーをピンポイントで合わせることができる。
これは単なる健康習慣を超えた、極めて合理的な予防戦略だと私は思います。
成長ホルモンと美肌サポート
さらに、夜納豆には美容やアンチエイジングを気にする方にも嬉しいメリットが期待できます。
納豆には、アミノ酸の一種である「アルギニン」が含まれています。
アルギニンには、脳下垂体を刺激し、通称「若返りホルモン」とも呼ばれる「成長ホルモン」の分泌を促す作用が知られています。
そして、この成長ホルモンの分泌が1日のうちで最も高まるのが、睡眠開始後の最初の3時間(深いノンレム睡眠中)なんです。
この時間帯は、日中に損傷した細胞の修復、筋肉の回復、そして肌のターンオーバー(生まれ変わり)が最も活発に行われる「ゴールデンタイム」とも呼ばれます。
夜に納豆を摂取することで、血中のアルギニン濃度と成長ホルモンの分泌ピークが同調し、このゴールデンタイムの働きを効率的にサポートしてくれる可能性が期待できるわけです。
美肌を目指すなら、試してみる価値はありそうですよね。
睡眠の質へのアプローチ
納豆には、アミノ酸の「トリプトファン」も含まれています。
トリプトファンは、体内でまず「セロトニン」(精神の安定)に変わり、その後、夜になると「メラトニン」(睡眠ホルモン)へと変化します。
これにより、自然な眠りを促し、睡眠の質を向上させるサポート役となる可能性もあります。
ナットウキナーゼ効果の持続時間

ねばねば研究所・イメージ
夜納豆のメリットをさらに強力に裏付けるのが、ナットウキナーゼの「作用時間」の長さです。
食べ物から摂った成分の効果って、なんとなく数時間で消えてしまうイメージがあるかもしれませんが、経口摂取(口から食べた)されたナットウキナーゼの血栓を溶かす力(線溶活性)は、食べた後、数時間から長いものでは8時間~12時間ほど持続するという研究報告もあるようです。
すごく長いですよね! 医療現場で点滴される血栓溶解薬の半減期が数十分程度であることを考えると、食品の成分としては驚異的な持続力です。(※これはあくまで私が調べた中での知識ですが!)
だからこそ、夜(例えば夕食時や就寝1~2時間前)に食べておけば、血栓リスクが最も高まる「深夜~早朝」の危険な時間帯を、その長い作用時間でしっかりとカバーできるというわけです。
これは本当に合理的だなと私は思います。
納豆ダイエットは夜が効果的?
「納豆はダイエットにも良い」とよく聞きますが、その場合はいつ食べるのがいいんでしょうか。
これも、「夜」に食べるのが効果的かもしれない、と言われています。
理由としては、まず夕食に納豆を加える(例えばご飯の前に食べる)ことで、豊富な食物繊維が食後の血糖値の急激な上昇を抑え、脂肪の蓄積を防ぐ効果が期待できること。
これが一つ目です。
そして二つ目が、先ほどお話しした「成長ホルモン」のサポートです。
睡眠中に成長ホルモンがしっかり分泌されると、脂肪の燃焼や筋肉の回復・成長が促されます。
筋肉量が増えれば基礎代謝も上がりますから、ダイエット中の体づくりを効率的にサポートしてくれる可能性が考えられます。
食べ過ぎには注意
ただし、ここで絶対に勘違いしてはいけないのが、「夜に納豆を食べれば痩せる」という魔法のような話ではない、ということです。
納豆も食品ですから、当然カロリーがあります。
1パック(約45g、タレ・からし込み)で80〜100kcal程度はあります。
夜に納豆を「追加」して、ご飯もいつも通り大盛りで食べていれば、当然カロリーオーバーになり、むしろ太ってしまいます。
あくまで「ダイエット中の不足しがちな栄養補給や、体づくりをサポートする」という位置づけで、食事全体のバランスの中で考えるのが良さそうですね。
納豆を朝夜両方食べるリスクと食べ方

ねばねば研究所・イメージ
朝も夜もこんなに良いところがあるなら、いっそ『朝夜両方』食べたら最強じゃない?…そう思う気持ち、すごく分かります。
私自身、本気でそう考えたこともあります。
でも、そこにはちょっと待った!と声を大にして言いたい、注意が必要な点があるんです。
食べ過ぎのリスクと、どうせなら効果的に食べたい「食べ方」のコツを、ここでしっかりチェックしましょう。
納豆1日2パックのデメリット
「朝夜両方」ということは、基本的に「1日2パック」を毎日食べることになりますよね。
納豆は紛れもないスーパーフードですが、さすがに2パックを「毎日」続けると、いくつかの懸念点が出てきます。
1日2パック摂取の懸念点
- カロリーオーバー: 納豆自体も2パックで160~200kcalになりますし、付属のタレの糖分や塩分も2倍になります。ご飯も2食分(朝・夜)しっかり食べれば、トータルのカロリーは思った以上に高くなります。
- 塩分の摂りすぎ: 付属のタレ1袋には約0.4g~0.5gの塩分が含まれます。1日2パック(タレも2袋)摂取すれば、それだけで約1.0gの塩分です。他の食事(味噌汁、漬物、おかず)も考えると、1日の塩分摂取目標量(成人男性7.5g未満、女性6.5g未満)を簡単に超えてしまい、むくみや高血圧のリスクを高める要因となり得ます。
- プリン体: 納豆はプリン体が「極端に多い」わけではありませんが、ゼロではありません。1日2パックを習慣にすると、尿酸値が気になる方や、痛風のリスクがある方は少し注意が必要かもしれません。
そして、これらカロリーや塩分よりも、私が一番気にしてほしいのが、一般に「健康成分」として知られている、次の「大豆イソフラボン」の過剰摂取リスクです。
大豆イソフラボンの過剰摂取とは

ねばねば研究所・イメージ
大豆イソフラボンは、ポリフェノールの一種で、女性ホルモンの「エストロゲン」と化学構造が似ているため、体内でホルモンみたいな働きをすることで知られています。
適量であれば、更年期症状の緩和や骨の健康維持など、私たちにとって有益な効果が期待されます。
ですが、何事も「過ぎたるは猶及ばざるが如し」です。
摂りすぎると、逆に体内のホルモンバランスを崩してしまい、月経周期の乱れや、婦人科系の不調などのリスクを高める可能性が指摘されているんです。
大豆イソフラボンの安全上限目安
日本の食品安全委員会は、健康な人が大豆イソフラボンを安全に摂取できる1日の摂取目安量の上限を 70~75mg(アグリコン換算値として)と設定しています。
一方で、納豆1パック(ミニパック約40g)に含まれる大豆イソフラボンは、データによれば約51mg とされています。
(※製品や豆の種類によってバラツキはあります)
この数字で計算してみると…
- 1日1パック(40g)摂取: 51mg (上限75mgの約68%)
- 1日2パック(80g)摂取: 102mg (上限75mgの約136%)
この計算が示す通り、納豆を1日2パック(朝夜両方)食べるだけで、それだけで安全上限値を大幅に超過してしまう計算になりますよね。
私たちは納豆以外にも、日常的に豆腐(1/4丁100gで約51mg)、味噌汁(1杯で約10mg)、豆乳(コップ1杯125gで約45mg)など、多くの大豆製品を食べています。(※含有量は目安です)
豆腐や豆乳と同じ感覚で納豆を2パック食べると、意図せずホルモン様作用物質を過剰摂取するリスクに直面します。
この点から、納豆を「朝夜両方(1日2パック)」毎日食べるのは、積極的におすすめできない、というのが私の考えです。
納豆とワーファリンの危険な関係
これは「デメリット」や「リスク」というレベルではなく、「絶対にダメ」という、医学的な禁忌(やってはいけないこと)事項です。
【最重要】ワーファリン服用中の方は厳禁です
血液をサラサラにするお薬(抗凝固薬)である「ワルファリン(商品名:ワーファリン)」を服用している方は、納豆を絶対に(一口も)食べてはいけません。
理由(相互作用): ワルファリンは、体内で「ビタミンK」の働きを邪魔することで、血液を固まりにくくします。
しかし、納豆には、他の食品とは比較にならないほど桁外れに豊富な「ビタミンK」が含まれています(納豆菌が生成するため)。
結果: 納豆から摂取された大量のビタミンKが、ワルファリンの薬効を完全に打ち消して(拮抗して)しまいます。
これにより、血栓予防の効果が失われ、脳梗塞や心筋梗塞のリスクが急激に高まる恐れがあり、非常に危険です。
健康な人には納豆の「ナットウキナーゼ」が血液をサラサラにする(血栓溶解)方向に働くのに、ワルファリンを飲んでいる方には納豆の「ビタミンK」が血液を固める(薬効阻害)方向に働く…。
これは納豆の持つ「パラドックス(逆説)」ですね。
ご自身やご家族に服用中の方がいる場合は、この情報を必ず共有してください。
必ず、医師や薬剤師の指示に厳格に従ってください。
(※ちなみに、ワルファリン以外の新しいタイプのお薬(DOAC/NOACと呼ばれるもの)では、納豆を食べても大丈夫な場合もありますが、自己判断は絶対にせず、必ず主治医にご確認くださいね!)
熱はダメ?効果的な納豆の食べ方

ねばねば研究所・イメージ
せっかく納豆を食べるなら、その栄養、特に注目の成分を最大限に活かしたいですよね。
特に「夜納豆」で血栓予防効果(ナットウキナーゼ)を期待する場合、最大の注意点は「熱」です。
ナットウキナーゼはタンパク質でできた「酵素」の一種なので、熱に非常に弱いんです。
一般的に70度以上になると、その働きが急速に失われ始めると言われています。
炊き立てのアツアツご飯(80度以上)に納豆を直接「オン」してしまうと、せっかくのナットウキナーゼが働かなくなってしまうかも…。
これはもったいないですよね。
血栓予防効果を一番の目的にするなら、ご飯を少し冷ましてから(人肌~60度くらい)納豆をかけるか、納豆ご飯ではなく「納豆だけ別で食べる」のが最も確実な方法です。
混ぜる回数は?
よく「納豆は100回、いや400回混ぜろ」なんて言いますが、実は混ぜる回数とナットウキナーゼの活性(量)は、直接はあまり関係ないとされています。
ただ、50回、100回とよく混ぜることで、納豆のうまみ成分である「グルタミン酸」などのアミノ酸が増したり、粘り気(ポリグルタミン酸)が空気を抱き込んで口当たりがまろやかになったりして、美味しくなるのは間違いないようです。
美味しく食べれば消化・吸収も良くなるかもしれませんし、何より食べるのが楽しくなりますよね!
栄養を逃さない食べ合わせ

ねばねば研究所・イメージ
納豆は単体でもすごいスーパーフードですが、他の食材と組み合わせることで、さらにパワーアップが期待できます。
いわゆる「相乗効果」ですね。
どうせなら、美味しくて健康効果もアップする「ちょい足し」を試してみませんか?
おすすめ「ちょい足し」レシピ
- 納豆 × キムチ これはもう定番中の定番ですが、最強の「発酵食品コンビ」です。納豆菌(善玉菌)とキムチの乳酸菌(善玉菌)が、ダブルで腸内環境をより強力にサポートしてくれます。食感のアクセントにもなりますよね。
- 納豆 × 酢(黒酢など) お酢の「クエン酸」が、ナットウキナーゼの働きと合わせて代謝アップを助けてくれるかも、と言われています。何より、味がさっぱりしてタレの代わりにもなり、減塩にもつながるのが嬉しいポイントです。
- 納豆 × 山芋(長芋) 山芋や長芋のすりおろし(とろろ)に含まれる消化酵素(アミラーゼなど)が、納豆のタンパク質やご飯のデンプンなどの栄養吸収を助けます。これらの酵素は熱に弱いので「生」のまま加えて食べるのが最適です。
- 納豆 × ニラ(ネギ類) ニラやネギ、玉ねぎなどに含まれる特有の香り成分「硫化アリル」は、納豆に含まれるビタミンB1(エネルギー代謝に不可欠)の吸収効率を高めてくれます。スタミナアップにも良い組み合わせですね。
他にも、オリーブオイル(脂溶性ビタミンKの吸収UP)や、卵黄(タンパク質強化)、シラス(カルシウム)など、いろんな組み合わせを試して、自分好みの最強トッピングを見つけるのも楽しいですよね。
納豆を朝か夜か両方かの最終結論
さて、「納豆を朝か夜か、それとも両方か」という、この悩ましい疑問について、ここまで見てきた情報を元に、私なりの結論をまとめたいと思います。
まず、健康維持の基本は「1日1パック」を推奨します。
「朝夜両方(1日2パック)」の日常的な習慣化は、大豆イソフラボンが安全上限値を容易に超過するリスクが、期待できるメリットを上回ってしまう可能性が高いと判断し、私はおすすめしません。
では、「朝」と「夜」、どちらか1パックを選ぶなら、どっちがいいか。
朝の「腸活・エネルギー補給」メリットも、日中のパフォーマンスを考えると非常に素晴らしいです。これは間違いありません。
ですが、納豆特有の強力な成分である「ナットウキナーゼ」の効果を、人体のリスク時間に合わせて最大化できるという点、さらに「成長ホルモン」の分泌ピークとアルギニンの作用が同調するという点を考えると、医学的・生理学的に見て「夜納豆」の明確な優位性が際立っているかな、と私は思います。
ねばねば研究所としての結論
もしどちらか迷ったら、「夜に1パック」を(ワルファリンを服用していない限り)試してみるのが、納豆の持つ特有の健康パワーを最も合理的かつ効率的に活かせる方法かなと思います!
もちろん、「朝の快便リズムを整えるために、朝納豆が欠かせない!」という方は、それを続けるのもまったく問題ない、素晴らしい健康習慣です。
最終的には、ご自身の健康目的(腸活優先か、血栓予防・美容優先か)やライフスタイルに合わせて、一番続けやすいタイミングで美味しく取り入れるのが一番ですね。
もしどちらか迷ったら、「夜に1パック」を(ワルファリンを服用していない限り)試してみるのが、納豆の持つ特有の健康パワーを最も合理的かつ効率的に活かせる方法かなと思います!
もちろん、「朝の快便リズムを整えるために、朝納豆が欠かせない!」という方は、それを続けるのもまったく問題ない、素晴らしい健康習慣です。
最終的には、ご自身の健康目的(腸活優先か、血栓予防・美容優先か)やライフスタイルに合わせて、一番続けやすいタイミングで美味しく取り入れるのが一番ですね。
この記事で紹介した内容は、あくまで私「M」が収集した一般的な情報に基づくものであり、特定の効果や安全性を保証するものではありません。
健康上の懸念がある場合や、お薬を服用中の方は、必ずかかりつけの医師や栄養士、薬剤師などの専門家にご相談くださいね。